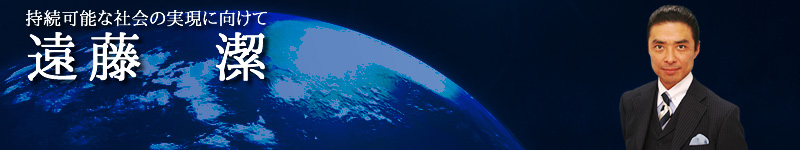
ニュースリリース|2009年
辻井喬 作家・詩人
2009.05.29
1951年東京大学経済学部卒業。その後、肺結核の療養を経て、衆議院議長だった父・康次郎の衆議院議長秘書を務める。この頃から詩を書き始める。1954年に西武百貨店に入社。1955年から取締役店長として百貨店を任される。同年、処女詩集『不確かな朝』を発表。1961年刊行の詩集『異邦人』で室生犀星詩人賞受賞。
1964年、父康次郎が死去。周囲からは清二が継承すると思われていた西武グループ総帥の座は、異母弟の堤義明が継ぐことになる。このような変動の下で、処女小説『彷徨の季節の中で』(1969年)は書き上げられた。
スーパーマーケットである西友を急展開し、業績を拡大。また西武百貨店を渋谷に進出させた。1969年、池袋西武の隣にあった百貨店「東京丸物」(まるぶつ)を、買収したばかりの小佐野賢治からさらに買収する形で経営を引き受け、府立十中の同級生だった増田通二を使いパルコを展開。
デベロッパーである西洋環境開発を通じ、ホテル経営、リゾート開発へも乗り出すなどセゾングループを形成(これには、父の不動産事業を継いだ義明への対抗心もあったと言われている)。マスコミも彼に注目し、財界の若きプリンスともてはやすようになる。
一方で、脱大衆文化と称して、DCブランドの展開や、無印良品などの事業も始める。田中一光、山本耀司らとの交流の中から、無印良品のヒントを得たといわれる。さらに、セゾン美術館など、メセナのさきがけといわれる活動も始める。1983年、自伝的小説『いつもと同じ春』で平林たい子文学賞受賞。
バブル崩壊後、急拡大の末にセゾングループの経営は破綻を迎え、1991年 には、グループ代表を辞任。92年、詩集『群青、わが黙示』を上梓し高見順賞受賞。 2000年には西洋環境開発(同年清算)を含むグループの清算のため、保有株の処分益等100億円を出捐した。
1980年代までは、「実業家・堤清二」の活動が主となり、「詩人/小説家・辻 井喬」は寡作だったが、セゾングループ代表辞任後は精力的に作家活動を展開。94年『虹の岬』で谷崎潤一郎賞受賞。先述した「父との確執と、父への理解」に加え、自身の特異なプロフィールに由来する、大企業の経営者というモデルを通じた「人間の複雑な内面」の描写が小説の特徴であり、『父の肖像』(2004年)はその集大成と言えよう。
1996年に堤清二名義で岩波書店から出版した「消費社会批判」を学位請求論文として、中央大学より博士 (経済学)の学位を取得(論文博士)。
堤義明が一連の不祥事で逮捕され、西武鉄道グループの再編・再建活動が活発化すると、義明への批判を展開。財界においては「経営者失格とされた人」であり、実業家としてはすでに引退した人物と認識されているが、異母弟の猶二と共に西武鉄道へ買収提案を行うなど、実業家、西武の創業者一族としての活動も展開している。
2000年には詩の業績で藤村記念歴程賞受賞、小説『風の生涯』で芸術選奨文部科学大臣賞受賞、2004年『父の生涯』で野間文芸賞受賞、2006年3月近作をはじめとする小説群の旺盛な創作活動により日本芸術院賞恩賜賞を受賞した。2007年日本芸術院会員となる。2009年『自伝詩のためのエスキース』で現代詩人賞受賞。
●堤清二
セゾングループ(旧・西武流通グループ)の実質的オーナー。文人社長としても知られ、小説家・詩人、辻井 喬(つじい たかし)の顔を持つ。財団法人セゾン文化財団理事長。日本ペンクラブ常務理事。日本文藝家協会常務理事。「歴程」同人。マスコミ九条の会呼びかけ人、憲法再生フォーラム共同代表、日中文化交流協会会長。中央大学より博士(経済学)(中央大学)。父は西武グループの創業者堤康次郎。
1964年、父康次郎が死去。周囲からは清二が継承すると思われていた西武グループ総帥の座は、異母弟の堤義明が継ぐことになる。このような変動の下で、処女小説『彷徨の季節の中で』(1969年)は書き上げられた。
スーパーマーケットである西友を急展開し、業績を拡大。また西武百貨店を渋谷に進出させた。1969年、池袋西武の隣にあった百貨店「東京丸物」(まるぶつ)を、買収したばかりの小佐野賢治からさらに買収する形で経営を引き受け、府立十中の同級生だった増田通二を使いパルコを展開。
デベロッパーである西洋環境開発を通じ、ホテル経営、リゾート開発へも乗り出すなどセゾングループを形成(これには、父の不動産事業を継いだ義明への対抗心もあったと言われている)。マスコミも彼に注目し、財界の若きプリンスともてはやすようになる。
一方で、脱大衆文化と称して、DCブランドの展開や、無印良品などの事業も始める。田中一光、山本耀司らとの交流の中から、無印良品のヒントを得たといわれる。さらに、セゾン美術館など、メセナのさきがけといわれる活動も始める。1983年、自伝的小説『いつもと同じ春』で平林たい子文学賞受賞。
バブル崩壊後、急拡大の末にセゾングループの経営は破綻を迎え、1991年 には、グループ代表を辞任。92年、詩集『群青、わが黙示』を上梓し高見順賞受賞。 2000年には西洋環境開発(同年清算)を含むグループの清算のため、保有株の処分益等100億円を出捐した。
1980年代までは、「実業家・堤清二」の活動が主となり、「詩人/小説家・辻 井喬」は寡作だったが、セゾングループ代表辞任後は精力的に作家活動を展開。94年『虹の岬』で谷崎潤一郎賞受賞。先述した「父との確執と、父への理解」に加え、自身の特異なプロフィールに由来する、大企業の経営者というモデルを通じた「人間の複雑な内面」の描写が小説の特徴であり、『父の肖像』(2004年)はその集大成と言えよう。
1996年に堤清二名義で岩波書店から出版した「消費社会批判」を学位請求論文として、中央大学より博士 (経済学)の学位を取得(論文博士)。
堤義明が一連の不祥事で逮捕され、西武鉄道グループの再編・再建活動が活発化すると、義明への批判を展開。財界においては「経営者失格とされた人」であり、実業家としてはすでに引退した人物と認識されているが、異母弟の猶二と共に西武鉄道へ買収提案を行うなど、実業家、西武の創業者一族としての活動も展開している。
2000年には詩の業績で藤村記念歴程賞受賞、小説『風の生涯』で芸術選奨文部科学大臣賞受賞、2004年『父の生涯』で野間文芸賞受賞、2006年3月近作をはじめとする小説群の旺盛な創作活動により日本芸術院賞恩賜賞を受賞した。2007年日本芸術院会員となる。2009年『自伝詩のためのエスキース』で現代詩人賞受賞。
●堤清二
セゾングループ(旧・西武流通グループ)の実質的オーナー。文人社長としても知られ、小説家・詩人、辻井 喬(つじい たかし)の顔を持つ。財団法人セゾン文化財団理事長。日本ペンクラブ常務理事。日本文藝家協会常務理事。「歴程」同人。マスコミ九条の会呼びかけ人、憲法再生フォーラム共同代表、日中文化交流協会会長。中央大学より博士(経済学)(中央大学)。父は西武グループの創業者堤康次郎。
*ニュースリリースの記事内容は発表日現在の情報です。
予告なしに変更され、ご覧になった日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承下さい。