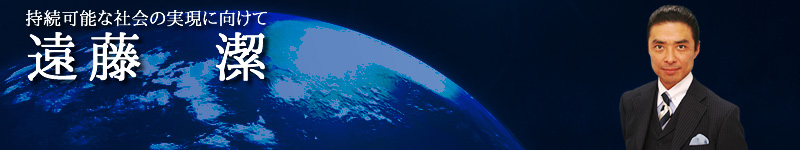
ニュースリリース|2009年
大橋照枝 麗澤大学経済学部教授
2009.04.22
いま、世界経済状況が深刻な様相を示しています。未曽有の世界不況とメディアはこぞってあおり、先進国のみならず途上国までもが、その出口を探しあぐんでいるようです。
戦後、私たちは、二度と戦争の愚を犯さぬことを約束し、ひたすら「豊かさ」を追い求めてきました。経済の大きさだけで目安を言うと、1985年には国民ひとりあたりGDPで世界第一位になり、以来1993年までの8年間は、我が国が真に世界第一位の「富める国」でした。経済的な豊かさがようやく実現したかに見えました。
その日本経済は、2008年の国民ひとりあたりGDPで世界22位、G7先進7カ国中最下位となり、マイナス成長下で経済力の優位も誇れるものではなくなりました。なぜ、この国はこんなにも希望のない、無策の国家になってしまったのでしょうか?
政治改革をはじめ、教育改革、行政改革、保険制度改革等々、いま、わたしたちは「改革」を合言葉に、かつての希望の持てる日本を取り返そうと様々な組織で改革が進められています。国民の誰もが「このままではいけない」ことに気づき、改革が進められています。しかし、この改革の、その先にある社会の姿が見えません。いったい、日本はどこへ向かおうとしているのでしょうか?
私たちが目指す社会は、どのような社会なのか。次の世代に向けた「持続可能な日本」への提言であり、「平成版幸福論」の提言です。幸福度調査で高い数値を示したスウェーデンでは、次世代や弱者を守るための環境諸法や、高福祉政策を背景にして、国の将来に希望を持っている若者が多く見られます。
経済が混迷するこの時期だからこそ、持続可能な社会指標をつくることが「幸福度、満足度の高い理想の社会」へと繋がります。
●大橋照枝
京都大学文学部哲学科社会学専攻卒業、(株)大広マーケティングディレクター、國學院大學栃木短期大學助教授を経て、現在、麗澤大学経済学部教授。博士(学術)、東京都地球環境保全アクションプラン検討会委員(1997年)農林水産省「農山村振興研究会」委員(2001年)などを歴任。
著作に「静脈系社会の設計」、「環境マーケティング」「「満足社会」をデザインする第3のモノサシ」「ヨーロッパ環境都市のヒューマンウェア」など多数。
戦後、私たちは、二度と戦争の愚を犯さぬことを約束し、ひたすら「豊かさ」を追い求めてきました。経済の大きさだけで目安を言うと、1985年には国民ひとりあたりGDPで世界第一位になり、以来1993年までの8年間は、我が国が真に世界第一位の「富める国」でした。経済的な豊かさがようやく実現したかに見えました。
その日本経済は、2008年の国民ひとりあたりGDPで世界22位、G7先進7カ国中最下位となり、マイナス成長下で経済力の優位も誇れるものではなくなりました。なぜ、この国はこんなにも希望のない、無策の国家になってしまったのでしょうか?
政治改革をはじめ、教育改革、行政改革、保険制度改革等々、いま、わたしたちは「改革」を合言葉に、かつての希望の持てる日本を取り返そうと様々な組織で改革が進められています。国民の誰もが「このままではいけない」ことに気づき、改革が進められています。しかし、この改革の、その先にある社会の姿が見えません。いったい、日本はどこへ向かおうとしているのでしょうか?
私たちが目指す社会は、どのような社会なのか。次の世代に向けた「持続可能な日本」への提言であり、「平成版幸福論」の提言です。幸福度調査で高い数値を示したスウェーデンでは、次世代や弱者を守るための環境諸法や、高福祉政策を背景にして、国の将来に希望を持っている若者が多く見られます。
経済が混迷するこの時期だからこそ、持続可能な社会指標をつくることが「幸福度、満足度の高い理想の社会」へと繋がります。
●大橋照枝
京都大学文学部哲学科社会学専攻卒業、(株)大広マーケティングディレクター、國學院大學栃木短期大學助教授を経て、現在、麗澤大学経済学部教授。博士(学術)、東京都地球環境保全アクションプラン検討会委員(1997年)農林水産省「農山村振興研究会」委員(2001年)などを歴任。
著作に「静脈系社会の設計」、「環境マーケティング」「「満足社会」をデザインする第3のモノサシ」「ヨーロッパ環境都市のヒューマンウェア」など多数。
*ニュースリリースの記事内容は発表日現在の情報です。
予告なしに変更され、ご覧になった日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承下さい。