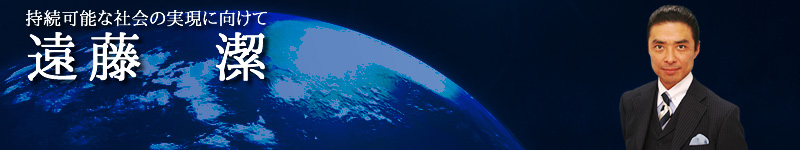
ニュースリリース|2015年
太田道灌公
2015.09.01
 遠藤 潔 遠藤宗家第十八代 父方祖母従兄弟である太田資和祖先の太田道灌は、文武両道に秀でた武将として名をはせ、東京発展の礎を築いた。
遠藤 潔 遠藤宗家第十八代 父方祖母従兄弟である太田資和祖先の太田道灌は、文武両道に秀でた武将として名をはせ、東京発展の礎を築いた。現在、石神井公園三宝寺池南側の台地には豊島氏が築いた石神井城跡の土塁や堀の跡が残っている。
石神井城は桓武平氏である豊島氏の本拠で、文明9年(1477年)に太田道灌に攻め落とされるまでは、豊島氏の領地経営の中心であった。
地域の範囲は明らかでないが、「石神井郷」は鎌倉時代には宇多氏の所領であったが、宮城氏、豊島氏と相伝し14世紀には豊島氏が本拠としたと考えられている。
石神井城を見渡す対岸の早稲田大学高等学院付近は城山遺跡であり、中世の堀が発掘され、石神井城攻めの際に太田道灌が陣を敷いた愛宕山と考えられている。石神井城落城後は太田道灌が領有し、曽孫にあたる新六郎康資に引き継がれた。
後に北条氏に安堵されて、その知行地になった。土支田と谷原在家(谷原・高野台)は太田氏の寄子であり、土支田源七郎と岸氏に配当された所領になっている。
天正18年(1590年)徳川家康公が江戸に入り、江戸幕府開府後は幕府直轄領(天領)となって幕末まで続いた。
石神井城跡は練馬区南西部にあたる地域である。
台地上を富士街道、それに沿って田柄用水、千川通りと千川上水が流れ、その間の石神井川の台地上に青梅街道がある。青梅街道は、甲州街道の脇往順環であり、太田道灌が江戸城築城の際、石灰を青梅から運搬した道筋でもあった。
●石神井城跡
石神井城は平安時代から室町時代まで石神井川流域に勢力を張った豊島氏の後期の日本の城であり、長尾景春の乱で没落するまで同氏が拠った。
*ニュースリリースの記事内容は発表日現在の情報です。
予告なしに変更され、ご覧になった日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承下さい。