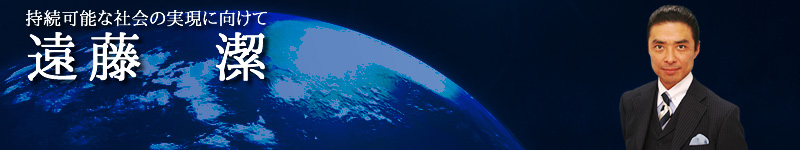
ニュースリリース|2012年
石井彰 エネルギー・環境問題研究所代表
2012.04.03
石井彰エネルギー・環境問題研究所代表は、明治時代に撮影された安芸の宮島や箱根の観光写真を示し、背景の山や森が丸裸に近いことを指摘した。石炭の利用により、薪を燃やさずに済むようになって、現在の植生が復活したと説明した。欧州でも同じ森林の破壊・再生プロセスが起きたという。
産業革命以前に比べ、世界人口は10倍、エネルギー使用は40倍に増えた。産業革命によって多くのものを大量に安価に作れるようになった。上下水道等の公衆衛生インフラが整備され、都市居住が増え、平均寿命は2倍に伸びた。ワットの蒸気機関ではなく、それを動かす石炭の使用開始こそが重要だった。現代文明の本質はエネルギーの大量使用である。
原発代替として脚光を浴びる太陽光発電の効率は薪炭・牛馬の2倍程度にすぎない。六本木ヒルズにある天然ガス燃料の自家用発電機とジャンボジェットの1基のエンジンの出力は同じ4万キロワット。太陽光発電だと、成田空港1期工事敷地の広さが必要で、その下の地面は草1本生えない。
「原発は放射能汚染という環境リスクを軽視し、再生可能エネは環境破壊リスクを軽視している」とした。どうすれば解決できるか。まず石炭・石油などCO2を大量に排出する燃料からガスに転換する。そして六本木ヒルズのように発電の排熱を空調や温水に利用するガスコージェネを増やす。原発にしろ再生可能エネにしろ、ひとつだけでエネルギー問題を解決するという考え自体が間違い。日本の課題は、世界一高い天然ガス輸入価格を引き下げることだ。
●石井彰
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)石油開発推進本部上席客員研究員。上智大学卒業後、日本経済新聞社記者を経て、石油公団で資源開発に携わる。80年代末からは石油・天然ガスの国際動向調査分析に従事。ハーバード大学国際問題研究所客員、パリ事務所長などを歴任。著書に『エネルギー論争の盲点 天然ガスと分散化が日本を救う』(NHK出版新書)など。
産業革命以前に比べ、世界人口は10倍、エネルギー使用は40倍に増えた。産業革命によって多くのものを大量に安価に作れるようになった。上下水道等の公衆衛生インフラが整備され、都市居住が増え、平均寿命は2倍に伸びた。ワットの蒸気機関ではなく、それを動かす石炭の使用開始こそが重要だった。現代文明の本質はエネルギーの大量使用である。
原発代替として脚光を浴びる太陽光発電の効率は薪炭・牛馬の2倍程度にすぎない。六本木ヒルズにある天然ガス燃料の自家用発電機とジャンボジェットの1基のエンジンの出力は同じ4万キロワット。太陽光発電だと、成田空港1期工事敷地の広さが必要で、その下の地面は草1本生えない。
「原発は放射能汚染という環境リスクを軽視し、再生可能エネは環境破壊リスクを軽視している」とした。どうすれば解決できるか。まず石炭・石油などCO2を大量に排出する燃料からガスに転換する。そして六本木ヒルズのように発電の排熱を空調や温水に利用するガスコージェネを増やす。原発にしろ再生可能エネにしろ、ひとつだけでエネルギー問題を解決するという考え自体が間違い。日本の課題は、世界一高い天然ガス輸入価格を引き下げることだ。
●石井彰
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)石油開発推進本部上席客員研究員。上智大学卒業後、日本経済新聞社記者を経て、石油公団で資源開発に携わる。80年代末からは石油・天然ガスの国際動向調査分析に従事。ハーバード大学国際問題研究所客員、パリ事務所長などを歴任。著書に『エネルギー論争の盲点 天然ガスと分散化が日本を救う』(NHK出版新書)など。
*ニュースリリースの記事内容は発表日現在の情報です。
予告なしに変更され、ご覧になった日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承下さい。