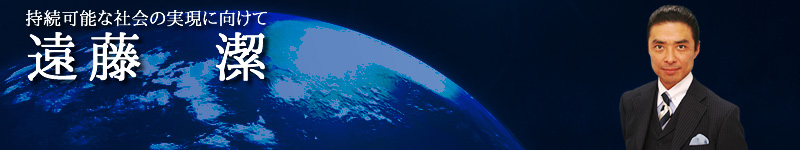
ニュースリリース|2015年
遠藤宗家と武士道
2015.08.01
 遠藤 潔 第十八遠藤宗家の由緒は、第五十代 桓武天皇を祖としながらも皇室を離れ、臣籍降下により平姓を賜る。日本の武士の特徴は、源氏が清和天皇を、平氏が桓武天皇を祖とするように、皇室を祖先にもつ。
遠藤 潔 第十八遠藤宗家の由緒は、第五十代 桓武天皇を祖としながらも皇室を離れ、臣籍降下により平姓を賜る。日本の武士の特徴は、源氏が清和天皇を、平氏が桓武天皇を祖とするように、皇室を祖先にもつ。皇室から分かれた貴族が、京の都を離れて地方の役職をもらい、そこで専門戦士として働くようになったのが、武士の由来である。それゆえ、源平の時代から徳川慶喜公まで、武士は天皇に権威を感じ、それを侵すことなく、逆に自分の権力の拠り所として仰いできた。本来、皇室から分かれた貴族の出身であるところに、武士の第一の特徴がある。藤原氏は、中臣鎌足が大化の改新の功により天智天皇に賜った「藤原」の姓が、子の藤原不比等の代に認められ、藤原(工藤)為憲の後裔・相良維兼が、遠江守に任ぜられ遠藤氏を名乗ったことに始まる。
第二の特徴は、戦闘のプロフェッショナルであること。武士は古くは「もののふ」といわれた。「もの」とは武器を意味す。「兵(つわもの)」「弓矢取る者」とも呼ばれた。弓矢や刀など武器を扱う軍事の専門家が、武士である。「侍(さむらい)」という名も、主君のそばで警護に当たる「さぶらふ」という言葉から来ている。戦闘者としての自覚は、長く平和の続いた江戸時代においても、武士の精神から失われることはなかった。ただし、「武」の究極は、その文字が表すように「矛を止める」ことであり、戦わずして勝つこととされた。
第三の特徴は、土地に密着した為政者であること。平安時代後期、辺境の防衛に当たった武士たちは、年月を経るうちに、その土地に定着し、自ら土地を開墾して、私営の田畑を営むようになった。こうして開墾領主となった武士は、「一所懸命」に領地を守り、広げ、受け継ぎ、競合しながら、巨大な集団へと成長していった。やがて、武士は、土地と領民を所有する為政者となった。そして、皇室の伝統と、儒教の政治道徳に学んで、領地・領国の経営に努めた。
これら三つの特徴とは、皇室から分かれた貴族の出身、戦闘のプロフェッショナル、土地に密着した為政者は、それぞれ尊皇・尚武・仁政という徳目に対応した。
こうした特徴と徳目をもつ武士たちは、平安後期から鎌倉・室町・戦国の時代を通じて、独自の倫理と美意識を生み出した。江戸時代に入って、それが一層、自覚的に表現された。これが、今日いうところの武士道である。
わが国は江戸時代に、徳川家康公が朱子学を幕府の教学とした。武士達は、外来の儒教を単に摂取するだけでなく、これを孔孟に戻って掘り下げて研究し、同時にこれに日本独自の解釈を加えた。
武士道は、この日本化した儒教を中心に、理論化・体系化がなされた。江戸時代には幕藩体制の下、平和な秩序が確立され、戦闘者としての武士の役割は、無用のものとなった。それゆえ、武士たちは、自己の存在意義を問い、武士のあるべき姿を強く意識するようになる。武士道が思想として錬成されたのは、そうした背景があった。
武士道は、日本固有の思想であり、日本人の精神的特徴がよく表れている。わが国は古来、敬神崇祖、忠孝一本の国柄である。そこに形成されたのが、親子一体、夫婦一体、国家と国民が一体の日本精神である。
日本精神の特徴は、武士道において、皇室への尊崇、主君への忠誠、親や先祖への孝養、家族的団結などとして表れている。そして、勇気、仁愛、礼節、誠実、克己等の徳性は、武士という階級を通じて、見事に開花・向上した。日本精神は、武士階級が現れた平安時代の後期10〜11世紀頃から約700年の武士の時代に、武士道の発展を通じて、豊かに成長・成熟したのである。
12世紀末には、源頼朝が鎌倉幕府を開いた。この時から約700年間、わが国では武士が政権を担う時代が続いた。戦士の階級が国を治めるという歴史は、わが国独特のものである。それゆえに、この数世紀の間に武士が創りあげた生き方や価値観は、日本独自の思想といえる。それが、武士道である。
明治維新は、武士道の発揮によって成し遂げられた。近代国家の建設の中で、身分としての武士は消滅した。しかし、国民国家の形成を通じて、武士道は国民全体の道徳となった。大東亜戦争の敗戦後、武士道は、失われつつあるものの、今なお日本精神の精華として、日本人の精神的指針として生き続けている。
●遠藤宗家
第五十代 桓武天皇を祖としながらも皇室を離れ、臣籍降下により平姓を賜る。
遠藤左太夫を始祖とする遠藤宗家(旗本家)は、徳川家康公が天正十八年(1590年)に江戸に入府し、慶長八年(1603年)に同地に幕府をひらき、爾後260年余、徳川将軍家 直参御目見得として日本の統治及び警備を行う。その後、明治元年(1868年)の明治維新以降、華族令の制定により明治十七年(1884年)に士族となり、十五代当主遠藤榮(大正天皇 宮内庁 東宮侍従)を経、現在(十八代当主輝)に至る。
*ニュースリリースの記事内容は発表日現在の情報です。
予告なしに変更され、ご覧になった日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承下さい。